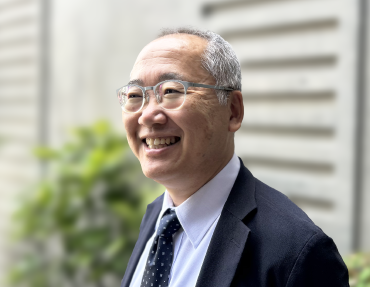公益社団法人 子どもの発達科学研究所が推進する
自治体、学校に向けた「いじめ予防授業」の取り組み
これまで文部科学省や教育委員会によるいじめ対策の中心は、いじめをいかに早く見つけ対応するか、でした。そのため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを多数配置したり、いじめ報告アプリや相談窓口を用意したりといったことが行われてきました。
これらはとても大切なことなのですが、よく考えてみると、こうした取り組みは、すべて「いじめが起きた」という事実から始まります。
いじめ早期発見から始まる支援は、子どもがいじめ被害に遭うという傷つき体験を許容しているわけなので、これをいくら一生懸命やっても、いじめそのものは減りません。
一方、多くの研究が、いじめはそのときだけでなく、将来にわたって深刻な影響を与えることを明らかにしています。つまり、私たちは、いじめ防止対策推進法を持ち出すまでもなく、いじめをなくさなければならないのです。
そこで、私たちはこれまでの多くの研究をベースに、日本の学校現場で実施可能ないじめ予防プログラムを開発しました。ちなみに、欧米諸外国では、オルヴェウスのいじめ予防プログラム、キヴァプログラムなど、エビデンスのあるいじめ予防プログラムが開発され、効果を上げています。これらをそのまま日本に持ち込もうという取り組みもありますが、学校のシステム、文化背景に違いがあることから、その取り組みには限界があると私たちは考えたのです。
私たちのいじめ予防プログラムは以下の3つから構成されています。
- いじめについての正しい知識を得る(考えを変える)
- いじめへの正しい対応行動を学ぶ(行動を変える)
- いじめが起きにくい集団を作る(集団を変える)
私たちはこの3つの変化を起こすためのプログラムを「トリプルチェンジ」と名づけました。
このトリプルチェンジを学校等で、子どもたちに学んでもらうメソッドが「いじめ予防授業」です。いじめ予防授業では、教員研修、授業案、ワークブック、動画教材をパッケージで提供しています。
また、私たちは他にもさまざまな角度から、先生方や保護者が子どもを見守るためのお手伝いを行っています。
以下、ご参考までに記載させていただきます。
調査ツール類
- いじめの申告やいじめの目撃報告ができるデジタル調査ツール「いじめDアンケート」
- 子どものための学校風土向上を目指すための調査ツール「学校風土調査」
- 子どもの日々の心身を見守る調査ツール「デイケン」
- 子どもたちのメンタルを見守る調査ツール「NiCoLi(ニコリ)」
研修等
- いじめのメカニズムを知り、いじめ予防と介入方法について学ぶ研修
- いじめ予防を学校に浸透させるためのリーダー育成研修
- いじめに関するエキスパートを各学校に置くための専門家育成研修

いじめに科学なんて通用するの?
いじめに科学を使うなんて、と驚かれる方が多いようですが、そうした方にお聞きしたいのは、「科学とは何か?」ということです。
科学について、様々な考え方があるでしょうが、ここでは「再現性」と表現しておきたいと思います。「〜〜したら、〜〜になる」という法則性であり、例えば、「〜〜という薬を飲んだら熱が下がった」というのも、たくさんの研究によって明らかになった法則性の積み重ねの上に成立しています。(だって同じ薬が、効いたり効かなかったりするのでは、安心してその薬を飲めないですからね。)
「いじめ」は、子どもの命や発達に深刻な影響を与えかねない大問題です。その「いじめ」を解決する、もしくは予防する、“薬”が欲しいですよね。
いじめは、実は日本特有の問題ではなく、世界中で問題になっています。いじめは、そのときだけの問題ではありません。いじめの被害者も、加害者も、傍観者でさえも、その後の発達に影響を与えることが分かっています。ですから、なんとしてもなくさなければならないのです。
ですので、世界の研究者が「いじめ」について日々、研究を行っていて、例えば、世界の研究の検索エンジンであるPub-medで、School Bullying(学校・いじめ)で検索すると、2014年から2023年の10年間で657本の論文がヒットするほどなのです。
つまり世界では、いじめに関する研究が日々、進んでいて、そうした科学的根拠(エビデンス)に基づいたいじめ対応をするのが当たり前であり、その効果についてもさらに研究が進んでいるのです。
いじめに科学は使えるのです。むしろ使うべきだと言えるでしょう。
いじめに負けるような子どもは社会に出ても通用しないんじゃないの?
(いじめはある意味、子どもを鍛えるために必要なんじゃないの?)
このように言う人は意外に多いと思います。いじめに負けた人は社会でも負ける、ということですが、それは誰が何を根拠に言い出したんでしょうか?もしかしたら“自分の力でいじめに負けずに成長した”と信じている、“成功者”の言葉かもしれませんね。
実は、こういうことを言う人は他の分野でも少なくありません(例えば、厳しい体罰をするコーチのおかげで、自分は成長できた、など)が、これをケーススタディと言います。
個人の経験に基づいた内容であり、“その人”の元々持っているスキル、人間関係、環境という条件があってこその内容です。例を挙げるならば、確かにその人はいじめに遭ったかもしれないけれど、元々、メンタルが強かった、仲間が多かった、逃げ場があった、など、その人特有の条件があって、いじめに負けなかった、ということです。
だいたい、その手の経験を語る人は、スポーツ選手や有名人など、社会的に地位があったり能力があったりする人かもしれません。そうでないと、そうしたことを発信できないからです。
ところが、ご承知の通り、誰もがそのような条件に恵まれているわけではなく、むしろそうでない人の方が大多数。特に今、まさにいじめに苦しんでいる子どもたちは、そうでないことが多いわけで、「いじめに負けるような子どもはダメだ」のようなメッセージは、子どもを傷つけることはあっても、絶対に助けにはならないのです。
それに、いじめ経験が将来に役に立つというエビデンスはいくら探してもありません。多くの研究が、いじめの被害が、自殺や成人期のメンタルヘルスの悪化に影響があるばかりか、就労や身体的健康、寿命にまで影響があることを指し示しています。
子どもの未来を考えたら、いじめは、絶対になくさなければならないのです。
いじめは子どもの世界のこと、大人が出るなんてかっこ悪いんじゃないの?
確かにいじめは子どもの世界で起こります(学校でさえ、いじめの現場に大人が居合わせられるのは、いじめ全体の1割程度という研究があります)。ただし、だからといって大人が解決に乗り出してはいけないという理由になりません。
加害者の子どもは、自分がいじめをしていることに気づいていない可能性があります(本書でも触れられているシンキングエラーの問題ですね)。ですから、子どもたちだけで解決できるかといったら、そうではありません。むしろ子どもたちは、解決の方法を大人から学ばなければならないのです。
ですので、大人がしっかりと介入しなければならないのですが、忘れてはならないことがあります。
一つ目は、被害者の安全を優先するということ。このくらい大丈夫、加害者が謝ったからよしにしよう、など、いろいろな考えがありますが、大切なのは、被害を受けた子どもが安心・安全な状況になること。それも、周りが考えた安心・安全ではなく、子ども自身が感じる安心・安全が大切です。それを最優先にしなければなりません。(場合によっては、安心・安全を確保するために、一時的に学校や幼稚園、保育園を休ませる、クラスを替えてもらう、加害者の子どもと離してもらう、などのが必要な場合があります。)
それからもう一つ、大人が冷静になり、正しい方法で子どものいじめ問題を解決するということ。
時々見られるのは、いじめられた子どもの親も、いじめたとされた子どもの親も、両方とも興奮して、互いに攻撃してしまうパターンです。我が子を守りたい気持ちは分かりますが、それを子どもたちは見ていて、何を感じるでしょうか? 決して良いモデルとはいえません。
ですので、ここは冷静になり、いじめられた子どもも、いじめた子どもも、両方とも発達の途中にあること、子どもたちの発達支援の観点から、いじめ解決を行うようにします。いじめは、いじめ防止対策推進法にあるように、どんな理由があってもしてはいけないことです。言葉で状況を整理し、加害者のシンキングエラーをただし、被害者の心を守りましょう。
※具体的ないじめ介入の方法、親がすべきことは、別著『いじめの科学』で詳しく解説しています。
「や・は・た 行動」って本当に通用するの?
絵本の中で、いじめ被害に遭ったときや目撃したときにすべきこととして、「や・は・た 行動」を紹介しています。「や」やめてという、「は」その場からはなれる、「た」たすけを求める、の3つです。
このことについて、「やめてと言えない子がいるのではないか」とか「その場からはなれようとしても、いじめっ子が追いかけてくるのではないか」、「助けを上手に求められない子がいるのではないか」などの指摘がされることがあります。
これはとても重要なポイントなので、考えてみていただきたいのですが、今、例に挙げたような「うまくいかない例」は、どのくらいの確率で存在するでしょうか?
もちろん、中にはそういう場合がありますし、そうしたときも何とかいじめを解決しなければなりませんが、「や・は・た 行動」がうまくいく例の方が圧倒的に多いはずなのです。そして、「うまくいった例」は、大きな問題にならないので、大人には見えなくなります(子ども自身もつらい経験にならず、忘れてしまいます)。
これが予防効果なのです。
この絵本の目的は、いじめ予防です。子どもは発達の途中ですから、いじめのようなことをしてしまう、起こしてしまうことがあるのですが、それを「誰も傷つかない」もしくは「傷付きが小さい」うちに、解決してしまう方がいいに決まっています。
絵本の解説部分で紹介していますが「や・は・た 行動」の一つ一つについて、効果があるというエビデンスがあります。効果がある、というのは、その行動をした方が、しないときに比べて、いじめが解決する、もしくは深刻化しない確率が高い、ということを意味しています。
子どもや状況によっては、うまくいかない場合があるでしょう。しかし、それでも「や・は・た 行動」は役に立ちます。子ども時代のいじめへの対応だけでなく、大人になってからも、様々な問題に直面したとき、私たちは「や・は・た 行動」を使っている可能性が高いのですから。
この絵本ができたわけ
いじめ防止対策推進法が施行されたのが、2013年。この法律によって、いじめ対策が明確になったのですが、ご承知の通り、その後もいじめ問題はなくなりません。それどころか、いじめに起因する自殺や不登校などの重大事態が増えています。
そんな中、私は2019年に『いじめの科学』を上梓しました。これは、いじめを情緒的、道徳的に扱うのではなく、科学的に検討しようという、当時としては画期的な内容だったと自負しています。おかげさまで、この『いじめの科学』は未だに注目を浴びているのですが、一方で、「理屈ばかり言っていても十分ではない。現場を変えてこそ、いじめ対策であるとも感じていました。
そこで、私が所長でもある公益社団法人 子どもの発達科学研究所から、各地の教育委員会、学校に対して、いじめ予防プログラム「トリプルチェンジ」を提供することにしました。このことにより、科学的に正しいいじめ対策が広まり、実際の学校現場においても、その効果が上がっているという報告を受けていました。
そうした状況のなか、世界文化社より、『いじめの科学』をベースにした絵本を出さないか、との話をいただいたのです。絵本出版については、だいぶ前から考えていましたので、大変魅力的な提案だと感じました。
『いじめの科学』を読んでいただくと分かりますが、いじめ対策は、いじめが起きてからではなく、いじめを起きないようにするという未然防止、予防を中心にすべきです。よって、子どもがなるべく小さいときから始めるというのは、非常に理にかなっているのです。
今回、絵本をつくるにあたり、「いじめの傍観者」に注目することにしました。なぜなら、傍観者こそ、いじめを解決し、いじめが起きにくい集団を作る鍵を握っていることは、既に多くの研究で明らかになっているからです。そして、私たちが開発し学校現場に提供している、いじめ予防プログラム「トリプルチェンジ」の思想そのものだからです。
幼少期から、いじめのことを正しく理解し、自分自身と、自分たちの友だちを守ることができる子どもに育てること、それがこの絵本のテーマになりました。
いじめが与える影響は大きく、そのときの悲しみや葛藤だけでなく、子どもの未来にも関連があります。いじめを予防することは、不登校、メンタルヘルスの悪化、自殺、非行などのリスクを下げ、健全な発達を保障するはずです。この絵本が、多くの保護者、支援者の目にとまり、子どもたちに届くことを祈っています。
この本を読んで、「こんなにうまくいくはずがない」「これでいじめがなくなるわけがない」と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、考えてみてください。子どもたちの世界からいじめをなくそうとするならば、まずは「いじめが何か」「いじめをどう捉えればいいのか」を子どもたちに明確に知らせ、スタンダードとなる「いじめへの対処の方法」を伝える必要があるのです。何しろ、日本にはそのスタンダードすらないため、子どもたちは「いじめが何か」を教えられていないのにもかかわらず、「いじめをやめなさい」「いじめはダメ」と言われ続けてきたのですから。
私たちの願いは一つです。子どもの健全な発達と豊かな未来の実現です。そのことが、現実になるように、いじめ問題にも一緒に立ち向かっていただきたいと願っています。
和久田学
プロフィール
作 和久田 学(わくた まなぶ)
公益社団法人子どもの発達科学研究所 所長/主席研究員静岡大学教育学部卒業。特別支援学校の教師として20年以上勤務した後、大阪大学大学院連合小児発達学研究科博士課程にて、小児発達学の博士号を取得。現在、大阪大学大学院連合小児発達学研究科招聘教員、浜松医科大学子どものこころの発達研究センター共同訪問研究員。専門はいじめや不登校など子どもの問題行動の予防、支援者トレーニング、介入支援プログラムなど。著書に『学校を変える いじめの科学』(日本評論社)、『科学的に考える子育て エビデンスに基づく10の真実』(緑書房)。